未必の戀の返りごと
8枚戻る
ようやく到着した苑宮の社の門の前では、顔に覚えのない老女が待ちかまえていた。まだ怠くて思うように動かない体を御堂島とサチカと二人がかりで車から降ろされる。別に望んできたわけではないし、面子を立てたくもない。しぶしぶといった様子を隠さずに御堂島と並んで立つと、貴臣の無礼な態度を全く意に介していないような恭しさで老女は頭を下げた。この老人が当主だろうか。当主会などでは苑宮はいつも欠席していたので顔を知らないのだ。
「次代の御津藏さまですね」
その声は、想像していたしゃがれ声とは全く違う、まるで少女のような声色を帯びていた。そのアンバランスさに、貴臣は相当な違和感を覚える。
「はい。こちらが、御津藏家当代当主の、貴臣様です」
御堂島は、他人向けの人当たりの良い笑顔でそう返した。
「事情は事前に聞き及んでおります」
どんな事情を聞き及ばせたのか。
貴臣は口車を回したであろう横の御堂島を伺ったが、彼はこちらを見なかった。
さあ、奥へ。
苑宮の当主に促されて、ようやくこちらを見た御堂島とちらりと視線を交わしてから、貴臣はその門をくぐった。
通された広間には三つ指をついて伏している巫女がずらっと並んでおり、それは大層壮観だった。揃って同じ着物を身につけて同じ髪型をしているところは、まるで学校のようだと思った。けれど、ここは学校と違って規則から外れた者が見あたらない。そう、例えば学校における貴臣や桐伍のような存在が居ないように見える。はずれなし、だ。
全員、ポケットティッシュだな。
貴臣は部屋には上がらず、廊下から一瞥しただけで立ち止まった。
「これが全部苑宮の巫女なの?」
「正確に申し上げますならば、この中から、適性のある者が苑宮の巫女となります」
老女はかしこまってそう答えた。
へえ。
そのシステムは違うなと思った。学校とだ。
「ま、いいや」
特に食指が動かなかったので、くるりと身を翻した。
「いいって……臣?」
困ったような声を出した御堂島を振り返らず、貴臣はもう一度同じ言葉を繰り返した。
「全然おいしそうじゃないから、いらない」
ふあ、と貴臣は欠伸をした。
「車戻って寝てるわぁ。後はよろしく」
ひらっと手を振って、貴臣は表情の読めない老女とため息を吐いた御堂島を置いてその場を去った。
御堂島の落ち込んだ様子を見て、すこしだけ胸が痛んだような気もした。
玄関で揃えてあった革靴を履き、誰もいない内玄関を出てからふと思い立って庭の方へと回った。
当然いちいち許可など取らないが、御津藏家当主の自分に文句を言える人間がこの家に存在するだろうか? しないだろう。いたとしても御堂島だし、あいつに対しては今多少憤っている。
屋敷の奥には行かないようにと言われていたが、住居部分に踏み込むつもりは毛頭なかった。興味があまりないからだ。巫女の暮らしというのは本で少し齧ったことがあるけれど、実際に見てみようとはその時も思わなかった。
立ち並ぶ白壁の倉をいくつか通り過ぎると、砂利が敷き詰められた庭に出た。奥には竹林があり、手前にはなんだかよくわからない背の低い木がいくつも生えている。飛び石が幾つか散らされていて、きっと雨の日などは綺麗だろうなと思った。
庭を見ることはわりと好きだった。
立場がら様々な所に連れ回される機会はいくらでもあって、けれどそういった時にまだ年齢が低い貴臣は顔を出すだけ出して放って置かれるので、そんなときは庭を見て過ごしていた。
苑宮の社というだけあって雰囲気は壮麗だったが、花はひとつもなかった。
それを少しつまらなく感じる。
春なのにね、と思った。
女はたくさんいたけれど、花はひとつも見つけられなかった。
はあ、とため息を吐くと、その瞬間やさしくて穏やかな風が貴臣の髪を揺らした。
生ぬるい温度。けれど、不思議とそれは気持ちの悪いものではなく。
そしてぞくりと背筋が震えた。
予感があった。
振り返り、上を見上げる。
倉だと思っていた白壁の高みにひとつだけ、まるで飾りじみた窓があった。真新しい木の格子と、嵌めこみ式のガラス。
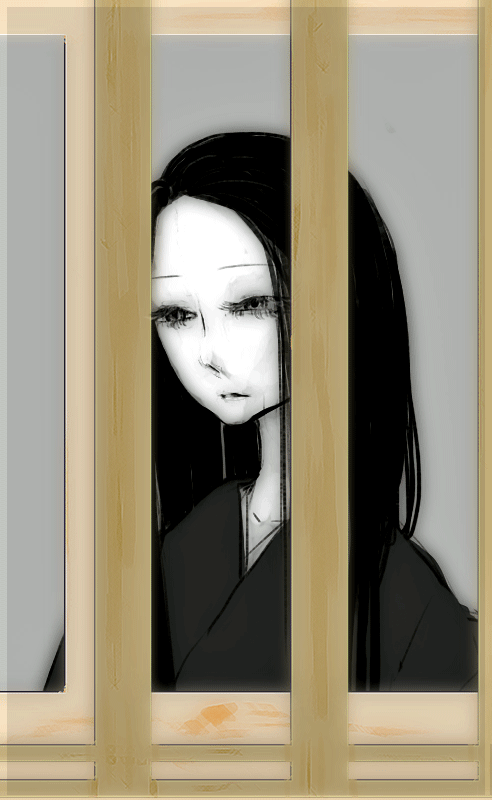
その向こうには、まるで名のある人形師に造られでもしたかのような少女の姿があった。それは、少女が見ていて眩しく感じてしまうような熱量の美人であるからではなく、彼女が誰の視線も温度も總て引きつけて吸い込んでしまうような虚ろさを持っているからだった。ひょっとすると何かの儀式に使う人形だろうか、と思った途端にその少女は瞬きをした。
ああ、花がないはずだ、と思った。
世の中の女が總て春である理由も知った。
あの女の子が冬だから、それ以外の存在は總てが春なのだ。
輝きもない穏やかさもない気高くもなくただうららかできっと永遠にやってこない。
喉が焼けつくように渇いた。
眼球の奥に、まばゆく閃く感情があった。
欲しいと思った。
これがきっと焦燥だ。はじめて、覚えた――食欲だ。
生まれて初めて、貴臣は自分が飢えていたことを知った。
こっちを向いてくれないか、そう考えた瞬間に少女は貴臣に気づいたらしい。それまで焦点の合っていなかった目を見開いて、一度瞬いた。
ああ――運命だ。
貴臣は、思わず胸に手を当てた。そこにある心臓は相変わらず動いていないのだけれど、どくんと跳ねたような気がしたのだった。
少女はしばし何かを思うように貴臣を見下ろしていたが、じきにふつりと後ろを向いて、そのまま窓の向こう、見えないところに行ってしまった。
胸に当てた手の指に力が入る。
唇を噛む。
目を細める。
胸に当てていた手を、ぶらんと体の横に垂らした。
ああ、会わなくちゃ。
あの子の名前を呼ばないと、この舌が焼けて溶けてしまう。
貴臣は、倉の入り口に向けて一歩踏み出した。